西安で感じたカルチャーギャップ
先日の中国・西安の視察でまず驚いたのが「喫煙所の多さ」でした。
日本だと「どこで吸えるのか?」とマップや標識を探すのが当たり前になっていますが、西安では逆に「どこでも喫煙所あるじゃん!」という感じ。喫煙者にとっては天国(?)、非喫煙者にとってはちょっと(かなり…)煙たい環境でした。

数字で見る中国の喫煙事情
中国国家衛生健康委員会の「中国喫煙健康影響報告2020」によると、喫煙者はなんと3億人超。人口の多さを考えると桁違いです。
-
15歳以上の喫煙率は1984年の33.9%から2018年には26.6%へ。
-
男性は61%から50.5%、女性は7%から2.1%まで減少。
減ってきてはいるものの、いまだに世界有数の喫煙大国。しかも毎年100万人以上がたばこ関連で亡くなっているという深刻な現実もあります。もし大幅に削減できなければ、2030年には年間200万人、2050年には300万人に増加する見込みだそうです。

日本と比べてみると
一方、日本の喫煙率はぐっと下がっています。厚生労働省「国民健康・栄養調査」(2019年)では、15歳以上の喫煙率は16.7%。男性27.1%、女性7.6%と中国より低い水準です。受動喫煙防止法や分煙の徹底により、街中での喫煙は厳しく制限され、喫煙所は専用の空間として隔離されつつあります。
喫煙所マップという日本の文化
この違いがよく表れているのが「喫煙所マップ」という存在です。
日本ではアプリやウェブで「どこに喫煙所があるか」を調べて移動するのが常識になりつつあります。駅や空港では専用ブース、街中ではガラス張りの小部屋、屋外では囲いがされたスペース。しかもそこから一歩出ると「路上喫煙禁止」で罰金という厳格さも。
ルールを守る日本社会では、喫煙者も決められた場所で吸うという暗黙の了解を徹底しているように見えます。西安のように「マップ不要でどこでも吸える文化」と比べると、同じ喫煙でも随分と印象が違いました。
健康問題への意識
中国も「健康中国2030」で喫煙率20%を目指していますが、現場での実感は「文化が追いついていない」というもの。日本もまだ喫煙者がゼロになったわけではありませんが、ルールと文化の両輪で「健康リスクを減らす仕組みづくり」が進んでいるように感じます。

視察で感じたこと
西安の街では、屋外はもちろん、世界遺産のそばやちょっとした広場にもゴミ箱とセットである喫煙所。しかも混雑していることもなく、喫煙者は自然体でたばこを楽しんでいました。日本で喫煙所難民になる光景とは真逆ですね。
旅行や視察では、こうした生活習慣の違いに触れるのも大きな学び。数字と現場の体験を重ねることで、健康と文化のギャップをより立体的に感じられました。

地図上で喫煙所がひと目でわかります!
喫煙所情報共有マップ





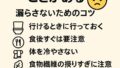

コメント